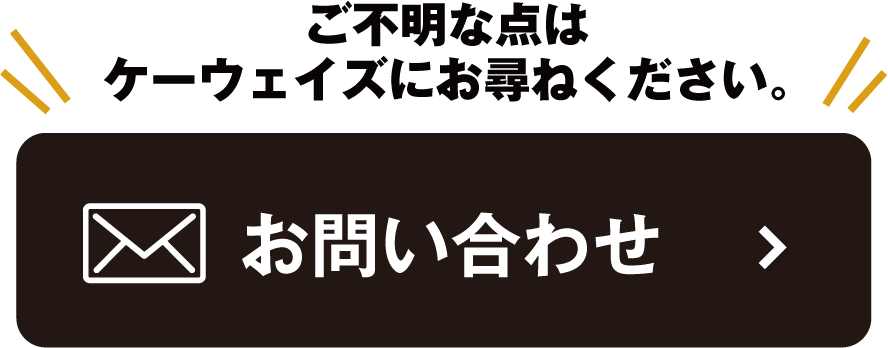RFIDとは
RFIDとは「Radio(無線) Frequency(周波数) IDentification(認識)」の略称で
読取機器(リーダー)の電波を用いてタグの情報を非接触で読み取り、書き込みする技術の総称です。
リーダーの形はハンディ式、定置型などがあり、タグの種類はバッテリーの有無や、読み取るための周波数で分類されています。
交通系ICカードもRFIDの一種です。
RFIDタグの構造
近年では用途によってさまざまなタグを選定することが可能です。
形や特長もさまざまですが、インレットを加工するという点で共通しています。
インレットとはアンテナ付きICチップのことで、RFIDタグはアンテナが電波を受け取りICチップが作動することで
非接触でのデータ読み取り、書き込みを行います。
インレットの周りのカバー部分をシール型、カード型、金属対応などに加工することで、さまざまな環境で利用できるタグになります。
RFIDの原理
周波数により多少の違いはありますが、RFIDタグとリーダー間のデータの流れは下記のとおりです。
- ①リーダーが電波を照射
- ②RFIDタグのアンテナが電波を受信
- ③ICチップの制御回路とメモリが作動
- ④RFIDタグ内のデータをリーダーへ送信
- ⑤リーダーがデータを受信
システムと組み合わせることで、受信したデータを処理することが可能です。
RFIDタグの種類
RFIDタグの分類方法は大きく分けて2つあります。
ひとつめはバッテリー搭載による分類、ふたつめは周波数による分類です。
・バッテリー搭載による分類
- パッシブタグ
- リーダーからの電力で起動する、バッテリーが内蔵されていないタイプのタグ
アクティブタグに比べて安価なため、アパレルや物流など様々な業界で活用されている
- アクティブタグ
- バッテリー搭載のため、電池の交換が必要
通信距離も長いため人やものの動きを管理するのに適している
- セミパッシブタグ
- パッシブタグとアクティブタグの両方の特徴を持ったタグ
通常はパッシブタグとして動作し、電波を受けたときのみアクティブタグとして動作する
レースタイムの自動計測などで活用されている
・周波数による分類
- UHFタグ
- UHFとは860~960MHzという超短波の周波数帯を用いた電波のこと
UHFタグで主に使用される周波数は920MHz
対象リーダーは1W版と250mW版があり、1W版は無線機扱いとなるため使用するためには申請が必要
- NFCタグ
- 13.56MHzの周波数を用いたタグ
スマートフォンの機種によっては読取ができるものもある
読取距離はUHFタグに比べると短く、10cm程度
それぞれの性質を活かし、様々な分野で活用されています。
RFIDタグの特長(UHFタグ)
- ・一括読取が可能
- ・探索が可能
- ・遮蔽物があっても読み取り可能
- ・データの書き換えが可能
- ・タグ自体の耐久性が高い
一括読取が可能
RFIDタグのいちばんの特長として一括読取があげられます。
近年はアパレル業界でRFIDタグの導入が増えてきたこともあり、タグを利用して棚卸作業を行う店舗も増えています。
2人で8時間かかっていた作業が1人で1時間で終わるようになったという実績もあり、業務効率化に加え、短縮された時間をほかの業務に充てることもできます。
探索が可能
RFIDタグは1枚ずつ読み取ることも可能です。RFIDタグに持っているデータを指定して読み取りを行うことで、読取対象が一つになるためもの探しに利用できます。
電波が届けば応答が返ってくるため、目視できる範囲にRFIDタグがなくても所在を確認することができます。
RFIDタグから返ってくる電波の強さを検知して画面に表示することで、おおよその方向や距離を知ることができます。
上記の特長を活かしてRFIDタグを指定して探索を行うことができます。
紛失した物品の探索や、ピッキング作業に適しています。
遮蔽物があっても読取可能
RFIDはリーダライタとタグの電波の送受信で成立しますので、遮蔽物が電波をさえぎらない材質であれば読取可能です。
例えば、段ボール箱の中に入っているRFIDタグも読み取ることができます。
この点は利用する環境によっては対象外のタグも読んでしまうというデメリットも発生するため、電波の強度を調整する、対象のタグを絞り込む(フィルター)などの対応が必要になります。
データの書き換えが可能
RFIDタグは内蔵しているICチップにデータを保持しています。リーダーには書き込みの機能もあるためRFIDタグのデータ書き換えも可能です。
チップメーカーにもよりますが約10万回の書き換えが可能で、工程管理などデータが順次変わっていく運用に適しています。
タグ自体の耐久性が高い
データ自体が印刷されているバーコードやQRコードに比べて、RFIDタグは耐久性が高いといえます。データはタグの内部に保存されているため、インレット(アンテナ付きICチップ)が破損しない限りはデータを読み取ることが可能です。
先述の通りデータの書き込みも可能ですので、一枚のタグが壊れるまで繰り返し使用することができます。
RFIDタグのデメリット
- ・コストがかかる
- ・読取精度が不安定
- ・システム面で考慮が必要
コストがかかる
タグの種類によって単価は異なりますが、RFIDタグ自体にもコストがかかります。
RFIDシステムを導入する際はタグ以外にもリーダーやシステムも不可欠ですので、トータルコストとしては高くなる傾向にあります。
コスト面が気になる場合は、部分的にシステム導入を行うなどの検討が必要になります。RFIDを活用するための初期費用と現在の作業に対する工数を比較衡量することも不可欠です。
読取精度が不安定
電波を受けることでRFIDタグが情報を返すため、電波を受け取りにくい状況になると読取精度が落ちてしまいます。
電波を受け取りにくい状況の理由はタグの向きや、タグを貼り付けている素材、周りの環境などです。
導入後に判明することを避けるためにも、環境テストを事前に実施することが不可欠となります。
システム面で考慮が必要
RFIDタグは単体で使用することはできず、必ずシステムが必要になります。
RFIDタグの特長として一括読取をあげましたが、運用環境によっては読み取りすぎてしまうこともあります。
その場合はシステムで読取対象タグを絞り込んだり、電波強度の調整をしたり、物理的にリーダーの配置や方向を調整する必要があります。
RFIDタグ利用システム事例
RFIDタグを活かした事例は多岐にわたります
-
■工程管理■ RFIDを使った製造業の工程管理アプリ
- 生産指示書にRFIDタグを取り付け、各工程の開始と終了でタグを読み取り工程管理を行います。
- 各工程の進捗状況が見えることにより各工程間の在庫状況の把握も可能となりました。
-
■電子ペーパータグ■ 電子ペーパータグスターターキット
- データだけでなく、表示部分も書き換え可能な電子ペーパータグの紹介です。
- 電子ペーパータグと書き込みに必要なリーダーライターと書き込みアプリのセットになっています。
ほかにもさまざまな事例、タグの種類があります
まとめ
RFIDにもメリットデメリットがあり、導入の際には現場の環境でタグやハードウェアの選定を行う必要があります。
弊社ではRFIDシステムのご相談はもちろん、タグのご提案も可能です。
ご不明点はお気軽にお問い合わせください!